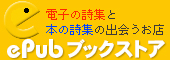岡島弘子「みえてくる」三百六十度 [something blue]
みえてくる 岡島弘子
山梨の山脈野坂をこえて
六十歳をこえて
今 私は三百六十度ひらけたところに出てしまった
スター・オブ・ホノルルの甲板に立つと
南国のいちまいの空と いちまいの大海原がひろがる
十二時の方向にクジラがいると おしえられて
目をこらす
周囲でどっと蕨市があがるか何もみつからず
なおも目をみひらく
なおも なおも 頭が海と同化するまで 青にそまるまで
みつめていると
あ
海と空をおしわけて
とつじょ あがる ふんすい
じゃなくて
いのちのいとなみがかたちを得たような
あれが潮吹き
なおもみつめていると 山が隆起する
こえてきたはずの小仏峠がハワイの海にあらわれた
と思ったがクジラのせなかだった
それはすぐ消え 尻尾がたかくあがる
御坂峠のように けわしく切れ込んだ稜線
が それはゆっくりうごいて
海原に太古の文字をえがいた
よみとれないうちに 消える
幼い日 蚊帳のなかでおよいだこともあった
ホノルルの海の群青色に波だつた蚊帳のなか
思い出にせなかを 直立させられて
私はなおもハワイの海を凝視する
クジラが八頭 イルカが九頭
西山連山のようにつらなり そして
尻尾があらわれ
太古の文字をえがいて消えた そのあいも
なおも目をこらす なおもなおも目をこらす
眼が海と同化するまで 海にそまるまで
目をこらす
海のひかりの果てまで
空のかがやきの果てまで
そのさきまで
むこうがわがみえてくるまて
※
初めの三行「山梨の山脈の坂をこえて 六十歳をこえて 今 私は三百六十度ひらけたところに出てしまった」はどんな意味か、この詩を更に読んでいくと深く深くわかります。
「意味」が「深くわかるというのは少し変な言い方ですが、この場合は他に言いようがありません。
幼い頃の「南国のいちまいの空」と今、目の前にひろがる「いちまいの大海原」が重なり合い、溶け合っていきます。
大海原を見つめていると、波が山になったり、峠になったかと思うと山々が鯨になったり、太古の文字になったりします。これが三百六十度ひらけたところなのです。
風景や場所は時を隔てて、私たちをつなげているようです。
「海のひかりの果て」「そらのかがやく果て」その先に何があるのか、わかりませんか、私たちはそこにむかっているような気がしました。
山田玲子「雨にぬれた木」でも思うのです [something blue]
雨にぬれた木 山田玲子
五十年まえ
わたしは堺市に住んでいました
二階の部屋の窓をあけると少し向こうに
石油コンビナートの建物がみえたのです
もっと前
二歳年うえの夫が子どもの頃に
そこは白砂青松の浜辺で
子どもたちは
家から裸足で泳ぎにいったということです
賑わっていた海岸
もうそのわが家はありません
家族のなかで
生きているのは わたしひとり
でも思うのです
横浜の中ほどに今住んで
雨にぬれた一本の木を眺めています
そのうちわたしもかならずいなくなる
でもこの木はなくならないでしょう
わたしより長生きするでしょう
桜も開き花見の人も集うでしょう
ふとわたし思います
わたしもやはり幸せなのだと
※
この詩はひと言でいうならば意味もとりやすく単純な詩です。でも、私はこの詩を宝物のように大切に大切にしまって置きたいという感じがします。お終いの節
でも思うのです
横浜の中ほどに今住んで
雨にぬれた一本の木を眺めています
そのうちわたしもかならずいなくなる
でもこの木はなくならないでしょう
わたしより長生きするでしょう
桜も開き花見の人も集うでしょう
ふとわたし思います
わたしもやはり幸せなのだと
を読むと何とも心が軽くなります。この節の前は一行開いていて、それが〈でも思うのです〉と始まります。私はここの処画とても好きです。
この明けた空白の一行に時の流れをありありと感じます。だからこそ、〈でも〉なのです。
そして最後に〈ふとわたし思います わたしもやはり幸せなのだと〉これはとても単純デ意味はよくわかります。たぶん私たちの幸せとはこういうことなのだと思います。
五十年まえ
わたしは堺市に住んでいました
二階の部屋の窓をあけると少し向こうに
石油コンビナートの建物がみえたのです
もっと前
二歳年うえの夫が子どもの頃に
そこは白砂青松の浜辺で
子どもたちは
家から裸足で泳ぎにいったということです
賑わっていた海岸
もうそのわが家はありません
家族のなかで
生きているのは わたしひとり
でも思うのです
横浜の中ほどに今住んで
雨にぬれた一本の木を眺めています
そのうちわたしもかならずいなくなる
でもこの木はなくならないでしょう
わたしより長生きするでしょう
桜も開き花見の人も集うでしょう
ふとわたし思います
わたしもやはり幸せなのだと
※
この詩はひと言でいうならば意味もとりやすく単純な詩です。でも、私はこの詩を宝物のように大切に大切にしまって置きたいという感じがします。お終いの節
でも思うのです
横浜の中ほどに今住んで
雨にぬれた一本の木を眺めています
そのうちわたしもかならずいなくなる
でもこの木はなくならないでしょう
わたしより長生きするでしょう
桜も開き花見の人も集うでしょう
ふとわたし思います
わたしもやはり幸せなのだと
を読むと何とも心が軽くなります。この節の前は一行開いていて、それが〈でも思うのです〉と始まります。私はここの処画とても好きです。
この明けた空白の一行に時の流れをありありと感じます。だからこそ、〈でも〉なのです。
そして最後に〈ふとわたし思います わたしもやはり幸せなのだと〉これはとても単純デ意味はよくわかります。たぶん私たちの幸せとはこういうことなのだと思います。
鷲谷みどり「フラミンゴ」言葉の旅 [something blue]
フラミンゴ 鷲谷みどり
フラミンゴたちは眠りのあいだ
木のように
夜のしずくを吸い上げている
この公園の
いきものたちは毎夜
四角い柵に自分の眠りを立てかけて
四角い夢を見るけれど
自分のかたちの上手な手放し方を
よく知らない私は
まだ うまく眠れない
彼らの眠りを一体何が支えているのか
植物のような関節で
ここにこうして立ち続けるために
一体どれほどの夜のしがいが そこに
井戸のように落とし込まれ続けなければならなかったのか
その疑問に答えようとして
なぜか私が足をもつれさせてしまう
この箱のなかの
うす赤いいのちの群れの中に ひとつだけ
張りぼていきものが立っているような
そんな不思議な間違いが この四角い柵に
眠っているような今夜
私は なんだか何度も
鳥たちの顔を覗き込んでしまう
鳥たちの夜の色をした目を覗き込んでから
私の夢のなかに
その紙のいのちの質感が消えない
かさこそとした音の
むせかえる夜の匂いのなかで
紙のいきものは 一体
どんな重心で
みずからのいのちをこらえているのか
息をつくたび ほどけていこうとする
その桃色のいのちの首とで今
とうやって夜の色をせき止めているのか
奥行きのない 淺い水の夢のなかで
あらゆるものから目から覚ましていても
あるはずのない私の体の底の井戸の
くらい水のたてる音からは
ついに起き上がることのできないまま
水辺の鳥たちは 夜明けを前に
自分の体の
上手な折り目を探している
※
とても不思議な感じのする詩です。
私は一度もこれほど鳥を見つめたこともないし、鳥の間近にいて、遂に鳥と一体化してしまうような
ことは、全く未経験なので、何が書いてあるのかよくわからないのですが、それにもかかわらず、先へ先へと読んでしまいます。
なぜそうなのかといえば、もしかしたら、この詩の言葉が持っている独特の力のせいかも知れません。
言葉と言葉として生まれる私たちの内側にも外側にも同時にある言葉、その言葉が生まれる前になにかしらあるもの、殆ど物質のようなもの(人によってはこれを「言霊」などといったりしますが私はこの言い方はあまり好きではありません)この詩人がめざしているのは、この言葉の基ではないでしょうか。
この言葉の基があるのは私たちを生み育てた場所かも知れません。
草野早苗「洞へ」詩の住処 [something blue]
洞へ 草野早苗
昔、島で戦いがあって
谷あいの集落の
全員が命を落とした
村人は自分の死が理解できず
今も地下で暮らしている
午後から夜にかけて
雨が止むとき
低い声が谷間に響くのはそのためだ
民宿の主人に言われた
明日の朝
村の裏口の鍾乳洞に行ってみたらいいと
小さな洞の近くに大きな洞があるらしいと
地質学者は言うけれど
大きな洞の入口がまだみつからないのだと
夜明け前
ちいさな鍾乳洞の入口から出入りする
半透明な人々
魚を持ち山菜を持ち
実直な姿で歩く
母親がこどもに何か言っているが言葉の意味がわからない
人々は私に向かい
声を出さずに会釈する
どうぞこちらへと手招きをする
ここに入ってはいけない
ついていつてはいけない
急な驟雨が谷間に降りそそぐ
午後までここにいてはいけない
紫色の島は西方向に遠ざかり
島の上にだけ
透けるように薄い青紫の
絹布のような雲がかかっている
私は自分のポケットに
方解石のかけらを見つけた
それは親指ほどの大きさで
夏の雨ほどの湿った匂いがした
※
それぞれの詩にはそれぞれの住処というか、次元というようなものがある感じがします。この詩ではそれが初めの一節ではっきりと姿を現しています。それは怪談仕立のようであり、オカルト風でもあります。
それにしても「村人は自分の死が理解できず」「今でも地下で暮らしている」という言葉には私はびっくり仰天してしまいました。そして、その意味が理解できないままにこの詩の住処をたどるように
読んでいくとそこには、「半透明な人々」や「言葉の意味が分からない人々」がいて話しかけようとします。
この怪談のような世界は決してグロテスクでも血なまぐさい感じがするものでもありません。
でも、とてつもない大きな穴が開いているような気がします。「自分の死を理解できず」「命をおとす」ことなどあるのでしょうか?
もとかしたら、あるのかも知れない。
ちょっと乱暴な言い方かも知れませんが、原爆や東北大震災、そしていまの日常の生活と思い浮かべてくると、私にはそのことが必ずしも怪談とはいいきれません。
ひとつの詩が心に残る野は、その詩の一行か、あるいはひとつの言葉があることによって、そうなる場合がよくあります。
「自分の死が理解できず」というのが、この詩のポイントであり、この詩の住処と思います。このことを私は最後の「方解石」によって実感するのです。この詩をよみながら私はカフカの「審判」の「犬のように殺された」というのを思い出しました。
b
昔、島で戦いがあって
谷あいの集落の
全員が命を落とした
村人は自分の死が理解できず
今も地下で暮らしている
午後から夜にかけて
雨が止むとき
低い声が谷間に響くのはそのためだ
民宿の主人に言われた
明日の朝
村の裏口の鍾乳洞に行ってみたらいいと
小さな洞の近くに大きな洞があるらしいと
地質学者は言うけれど
大きな洞の入口がまだみつからないのだと
夜明け前
ちいさな鍾乳洞の入口から出入りする
半透明な人々
魚を持ち山菜を持ち
実直な姿で歩く
母親がこどもに何か言っているが言葉の意味がわからない
人々は私に向かい
声を出さずに会釈する
どうぞこちらへと手招きをする
ここに入ってはいけない
ついていつてはいけない
急な驟雨が谷間に降りそそぐ
午後までここにいてはいけない
紫色の島は西方向に遠ざかり
島の上にだけ
透けるように薄い青紫の
絹布のような雲がかかっている
私は自分のポケットに
方解石のかけらを見つけた
それは親指ほどの大きさで
夏の雨ほどの湿った匂いがした
※
それぞれの詩にはそれぞれの住処というか、次元というようなものがある感じがします。この詩ではそれが初めの一節ではっきりと姿を現しています。それは怪談仕立のようであり、オカルト風でもあります。
それにしても「村人は自分の死が理解できず」「今でも地下で暮らしている」という言葉には私はびっくり仰天してしまいました。そして、その意味が理解できないままにこの詩の住処をたどるように
読んでいくとそこには、「半透明な人々」や「言葉の意味が分からない人々」がいて話しかけようとします。
この怪談のような世界は決してグロテスクでも血なまぐさい感じがするものでもありません。
でも、とてつもない大きな穴が開いているような気がします。「自分の死を理解できず」「命をおとす」ことなどあるのでしょうか?
もとかしたら、あるのかも知れない。
ちょっと乱暴な言い方かも知れませんが、原爆や東北大震災、そしていまの日常の生活と思い浮かべてくると、私にはそのことが必ずしも怪談とはいいきれません。
ひとつの詩が心に残る野は、その詩の一行か、あるいはひとつの言葉があることによって、そうなる場合がよくあります。
「自分の死が理解できず」というのが、この詩のポイントであり、この詩の住処と思います。このことを私は最後の「方解石」によって実感するのです。この詩をよみながら私はカフカの「審判」の「犬のように殺された」というのを思い出しました。
b
植木信子「便り」 詩を歩く [something blue]
便り 植木信子
薄青い空間に
靄に覆われて笑っているひと
泣いているような
西の空は夕日があかい
誰なんだ 何故なんだ
朱色したとても大きい秋なんだ
黄金色の稲穂に刈り取りのすんだ茶色の田がまじり
遠くの山並みがあおい
すすきの穂が光って
白鳥のように下りの列車がすべっていく
ふるさとの便りを届けるなら
柿の実色した夕日が眩しくて どこかに
すすきだけの原があるのです
白い穂並みが海原のようにつづく真中を
道がまっすぐに延びている
誰かが一人その道をゆく
道は夕日に向かって延びていて
地平に消えていきます
日も暮れて
祝歌、太鼓も鳴って
びしょうぶつが影を落とします
暗い洞をぬけた半円の陽のなかに佇むひとがいます
はさ木の交叉する道で声をだしてわらうので
昔きいたあなたのようなので振り返ります
月画のぼって 田園は沈んでいって
星も落ちてくるようです
街の灯が懐かしく
秋の夜長
ふるさとに便りをしたためるなら
今年もお酒ができました お茶もうまく実りました
追伸として
秋深い行道です
暮れた大地のはさ木の辻にはびしょうぶつが並んで
影を落としています…と
※びしょうぶつ 木喰いが作ったとされている微笑をうかべた一本彫りの簡素の木像
※はさ木 刈りとった稲を干す木
※ この詩を読んでいくと、どこかへ導かれていくようです。突然「誰なんだ 何故なんだ」と大きな声が
きこえてきて、とてもびっくりしました。でも、道は先の方に続いているようで、辿って行かずにはいられません。
その風景はひとつひとつ細やかで思わず見とれてしまいます。なつかしいようでもあり、初めてのようでもあります。
いつの間にか日常から夢の世界へ、あるいは生の世界から死の世界へ導かれていきそうで、少し
怖い感じです。
決してどこへたどり着くのか、わからないので、それが不安です。その一方で、私はこの詩を読みながら、宮澤賢治の世界や災害にあった東北のことなどを思い浮かべたりしました。
多分、ここには「詩の道」があるのでしょう。それは宇宙の星のように人間の世界をめぐっています。
多分、ひとの詩の道はひとつの星の道と同じように無限の時空に向かってひらかれているのでしょう。だから、この詩人は明日になると何の苦もなく、全く新しい朝を迎え、詩の道を歩き始めるのでしょう。
「便り」というのは、多分、この人にとって詩の別名なのでしょう。。
薄青い空間に
靄に覆われて笑っているひと
泣いているような
西の空は夕日があかい
誰なんだ 何故なんだ
朱色したとても大きい秋なんだ
黄金色の稲穂に刈り取りのすんだ茶色の田がまじり
遠くの山並みがあおい
すすきの穂が光って
白鳥のように下りの列車がすべっていく
ふるさとの便りを届けるなら
柿の実色した夕日が眩しくて どこかに
すすきだけの原があるのです
白い穂並みが海原のようにつづく真中を
道がまっすぐに延びている
誰かが一人その道をゆく
道は夕日に向かって延びていて
地平に消えていきます
日も暮れて
祝歌、太鼓も鳴って
びしょうぶつが影を落とします
暗い洞をぬけた半円の陽のなかに佇むひとがいます
はさ木の交叉する道で声をだしてわらうので
昔きいたあなたのようなので振り返ります
月画のぼって 田園は沈んでいって
星も落ちてくるようです
街の灯が懐かしく
秋の夜長
ふるさとに便りをしたためるなら
今年もお酒ができました お茶もうまく実りました
追伸として
秋深い行道です
暮れた大地のはさ木の辻にはびしょうぶつが並んで
影を落としています…と
※びしょうぶつ 木喰いが作ったとされている微笑をうかべた一本彫りの簡素の木像
※はさ木 刈りとった稲を干す木
※ この詩を読んでいくと、どこかへ導かれていくようです。突然「誰なんだ 何故なんだ」と大きな声が
きこえてきて、とてもびっくりしました。でも、道は先の方に続いているようで、辿って行かずにはいられません。
その風景はひとつひとつ細やかで思わず見とれてしまいます。なつかしいようでもあり、初めてのようでもあります。
いつの間にか日常から夢の世界へ、あるいは生の世界から死の世界へ導かれていきそうで、少し
怖い感じです。
決してどこへたどり着くのか、わからないので、それが不安です。その一方で、私はこの詩を読みながら、宮澤賢治の世界や災害にあった東北のことなどを思い浮かべたりしました。
多分、ここには「詩の道」があるのでしょう。それは宇宙の星のように人間の世界をめぐっています。
多分、ひとの詩の道はひとつの星の道と同じように無限の時空に向かってひらかれているのでしょう。だから、この詩人は明日になると何の苦もなく、全く新しい朝を迎え、詩の道を歩き始めるのでしょう。
「便り」というのは、多分、この人にとって詩の別名なのでしょう。。
大石ともみ「天秤ばかり(三)」おいしい詩 [something blue]
天秤ばかり(三) 大石ともみ
私は物の重さを量るよろこびは
その沈黙を聴くこと と
洋菓子店の閨房で
小さな天秤ばかりは
また語りはじめた
一グラムの分銅に見合う粉砂糖
二つの皿が 揺れ定まると
粉砂糖には
沈黙が降りてくる
沈黙に 在って
静寂に 無いもの
万華鏡の軽やかさで
沈黙は 澄んだ一音で
透明な旋律をかすかに響かせる
物の重さを量るよろこびは
沈黙の旋律が
祈りの音色に聞こえると と
一グラムの粉砂糖を量り終えた
古典的な道具は
哲学者の眼差しでこう語った
※
私が面白詩と考える詩のなかには時に「おいしい詩」としか言いようのないものがあります。
この詩はその代表的なものです。
この詩ができるまでは多くのの年月や時間か体積しているような感じがします。
でも、この詩はとてもみずみずしく、小さな子供や木の芽のように柔らかです。これらの言葉がどこから来て、どこへ向かっていくのか、私には分かりませんが、この詩を読む私を甘く包んでいることは
確かです。
宇宙はどこにあるのかわかりません。このお菓子屋さんもどこにあるのかわかりません。
でも、必ずあるような気がします。それはこれらの言葉が喜びながら歌っているからです。
永い時間生きてきたからこそ、伝わるものがあります。それはたとえば私の好きなシュベルヴェーイルの詩に「馬はふりむいて 誰も見ないものを見た」というのがあります。
私はこの天秤に同じようなものを感じます。
それは私たちの間近にありながなら決して見たり、触れたりすることがめったにない極上のお菓子のようなものなのでしょう。
私は物の重さを量るよろこびは
その沈黙を聴くこと と
洋菓子店の閨房で
小さな天秤ばかりは
また語りはじめた
一グラムの分銅に見合う粉砂糖
二つの皿が 揺れ定まると
粉砂糖には
沈黙が降りてくる
沈黙に 在って
静寂に 無いもの
万華鏡の軽やかさで
沈黙は 澄んだ一音で
透明な旋律をかすかに響かせる
物の重さを量るよろこびは
沈黙の旋律が
祈りの音色に聞こえると と
一グラムの粉砂糖を量り終えた
古典的な道具は
哲学者の眼差しでこう語った
※
私が面白詩と考える詩のなかには時に「おいしい詩」としか言いようのないものがあります。
この詩はその代表的なものです。
この詩ができるまでは多くのの年月や時間か体積しているような感じがします。
でも、この詩はとてもみずみずしく、小さな子供や木の芽のように柔らかです。これらの言葉がどこから来て、どこへ向かっていくのか、私には分かりませんが、この詩を読む私を甘く包んでいることは
確かです。
宇宙はどこにあるのかわかりません。このお菓子屋さんもどこにあるのかわかりません。
でも、必ずあるような気がします。それはこれらの言葉が喜びながら歌っているからです。
永い時間生きてきたからこそ、伝わるものがあります。それはたとえば私の好きなシュベルヴェーイルの詩に「馬はふりむいて 誰も見ないものを見た」というのがあります。
私はこの天秤に同じようなものを感じます。
それは私たちの間近にありながなら決して見たり、触れたりすることがめったにない極上のお菓子のようなものなのでしょう。
神泉薫「忘却について」地平線 [something blue]
忘却について 神泉薫
わたくしたちがいま
忘却しているのは
もっとも等しく大地を照らしている 太陽
もっとも明るく夜空をてらしている 一番星
もっとも無防備な裸足に優しい 土の温もり 砂浜の清々しさ
季節に傾く雨の匂い静かな小鳥のさえずり
枝を這うカタツムリの歩みの ゆったりとした時間の豊饒
手をつなぐこと
頬に触れること
本当はひとつの椀で充ち足りること
充ち足りれば 永遠に争いは起こらないということ
「生き方はいくらでもある
ひとつの中心点からいくらでも半経がひけるように」
と綴った
ウォールデン湖畔に住んだH・D・ソローのまなざし
着こみ過ぎた衣類に
隠れてしまった新しい肌があること
人工の偽の皮膚を脱いで
大いなる自然の大気に まるごとさらさらされること
冬の時代に流され 翻弄され
掛け違えた胸のボタンを正す指がかじかんでいる
わたくしたち
生の中心に屹立する一本の志の鋤で
柔らかくも逞しい心を耕すこと
ときには
開いたままではなく
忙しない瞳を閉じること
さらなる沈黙のために 饒舌な書物を閉じること
閉じた視界の裡には
深々とした漆黒の夜が開かれ
決して忘却してはならない
もっとも強靱な人間の孤独が
生い茂る森のように目覚めている
※
この詩は警句のようであり、論理的緊張をはらんでいながら、しかも、どこか抒情的です。
冒頭の<わたくしたちがいま/忘却しているのは>という問いが柱となって、その周りに壁や窓がつけられていくような感じがします。それらはひとつひとつ温もりがあり、やさしく、みずみずしい。
だから安心してひとつひとつの言葉に導かれ、建物のなかを眺めて行くことができるのです。
その光景はときには今まで見たことがあるようなものであったりしますが、それにもかかわらず、初めの<わたくしたちが/忘却しているのは>という柱がしっかりと屹立しているから、全く新しいものと
なります。
そして、このことが最も単的に現れているのが最後の三行です。
<決して忘却してはならない
もっとも強靱な人間の孤独が
生い茂る森のように目覚めている>
警句は外に向かって発せられるものであるが、この詩の場合明らかに内側に向かっても発せられている。これがこの魅力なのです。。
わたくしたちがいま
忘却しているのは
もっとも等しく大地を照らしている 太陽
もっとも明るく夜空をてらしている 一番星
もっとも無防備な裸足に優しい 土の温もり 砂浜の清々しさ
季節に傾く雨の匂い静かな小鳥のさえずり
枝を這うカタツムリの歩みの ゆったりとした時間の豊饒
手をつなぐこと
頬に触れること
本当はひとつの椀で充ち足りること
充ち足りれば 永遠に争いは起こらないということ
「生き方はいくらでもある
ひとつの中心点からいくらでも半経がひけるように」
と綴った
ウォールデン湖畔に住んだH・D・ソローのまなざし
着こみ過ぎた衣類に
隠れてしまった新しい肌があること
人工の偽の皮膚を脱いで
大いなる自然の大気に まるごとさらさらされること
冬の時代に流され 翻弄され
掛け違えた胸のボタンを正す指がかじかんでいる
わたくしたち
生の中心に屹立する一本の志の鋤で
柔らかくも逞しい心を耕すこと
ときには
開いたままではなく
忙しない瞳を閉じること
さらなる沈黙のために 饒舌な書物を閉じること
閉じた視界の裡には
深々とした漆黒の夜が開かれ
決して忘却してはならない
もっとも強靱な人間の孤独が
生い茂る森のように目覚めている
※
この詩は警句のようであり、論理的緊張をはらんでいながら、しかも、どこか抒情的です。
冒頭の<わたくしたちがいま/忘却しているのは>という問いが柱となって、その周りに壁や窓がつけられていくような感じがします。それらはひとつひとつ温もりがあり、やさしく、みずみずしい。
だから安心してひとつひとつの言葉に導かれ、建物のなかを眺めて行くことができるのです。
その光景はときには今まで見たことがあるようなものであったりしますが、それにもかかわらず、初めの<わたくしたちが/忘却しているのは>という柱がしっかりと屹立しているから、全く新しいものと
なります。
そして、このことが最も単的に現れているのが最後の三行です。
<決して忘却してはならない
もっとも強靱な人間の孤独が
生い茂る森のように目覚めている>
警句は外に向かって発せられるものであるが、この詩の場合明らかに内側に向かっても発せられている。これがこの魅力なのです。。
清水弘子「思イダシテクレロ」在るけどない [something blue]
思イ出シテクレロ 清水弘子
川に寄り添う緑の丘陵の川向かいに暮らしている ここから見ると丘
陵は 伏した大きな生きもののかたち そんな丘陵をゴンドウと名付け
川沿いの土手道を十年散歩して
犬が透明になってもいっしょに散歩して
まいにち川向こうのゴンドウを愛でる
ゴンドウはますますゴンドウになり
夕くらやみ
身体をふたまわり大きくして
かすかにうごく背中の気配の
こちらの頬まで触れてきて
何度もわたしに言ってくる
モットモット思イ出シテクレロ
何百何千年前ノ
此処ノコト オレノコト
トップリ其処ニ沈メルクライ
思イ出シテクレロ
わたしの受け継ぐ
わたし以前のものたちは
忘却の厚い真綿をなぞるだけ
わたしをせつなくさせるだけ
そういえば
お前のすがたはここから見ると
古い都の
古墳みたいだと言ってやると
あの犬みたいに
ない尻尾をぶんぶんふる
いない犬の伏したかたちになって
ソウソウ ソレカラ ソレカラ
こんなわたしに
在るけどない
ないけど在る
そんなものを紡げという
※
この詩のはじめの二行に出会ったとき私は背中がぞくぞくする程感動しました。「犬が透明になっても」とは犬が死んだことなのでしょうが、それがわかると、透明な犬が本当に一緒にいるようで、びっくりしました。この二行は私にとって、この詩全体を決定するようなものでした。
この二行によって、というか、「犬が透明になっても」という言葉を通して全く世界が新しく見えはじめたのです。それはまさに別世界の扉のようでさえありました。
それから、二連三連と続く古代ゴンドウとの交流や対話などもとても面白いのですが、それも、この
透明な犬と同じ世界なのだと思います。
その世界は何億年も超える時間の中で生きものがお互いに言葉を交わしたり、愛し合ったりすることです。「在るけとない ないけど在る」を紡ぐのは透明な犬なのだと思います。
川に寄り添う緑の丘陵の川向かいに暮らしている ここから見ると丘
陵は 伏した大きな生きもののかたち そんな丘陵をゴンドウと名付け
川沿いの土手道を十年散歩して
犬が透明になってもいっしょに散歩して
まいにち川向こうのゴンドウを愛でる
ゴンドウはますますゴンドウになり
夕くらやみ
身体をふたまわり大きくして
かすかにうごく背中の気配の
こちらの頬まで触れてきて
何度もわたしに言ってくる
モットモット思イ出シテクレロ
何百何千年前ノ
此処ノコト オレノコト
トップリ其処ニ沈メルクライ
思イ出シテクレロ
わたしの受け継ぐ
わたし以前のものたちは
忘却の厚い真綿をなぞるだけ
わたしをせつなくさせるだけ
そういえば
お前のすがたはここから見ると
古い都の
古墳みたいだと言ってやると
あの犬みたいに
ない尻尾をぶんぶんふる
いない犬の伏したかたちになって
ソウソウ ソレカラ ソレカラ
こんなわたしに
在るけどない
ないけど在る
そんなものを紡げという
※
この詩のはじめの二行に出会ったとき私は背中がぞくぞくする程感動しました。「犬が透明になっても」とは犬が死んだことなのでしょうが、それがわかると、透明な犬が本当に一緒にいるようで、びっくりしました。この二行は私にとって、この詩全体を決定するようなものでした。
この二行によって、というか、「犬が透明になっても」という言葉を通して全く世界が新しく見えはじめたのです。それはまさに別世界の扉のようでさえありました。
それから、二連三連と続く古代ゴンドウとの交流や対話などもとても面白いのですが、それも、この
透明な犬と同じ世界なのだと思います。
その世界は何億年も超える時間の中で生きものがお互いに言葉を交わしたり、愛し合ったりすることです。「在るけとない ないけど在る」を紡ぐのは透明な犬なのだと思います。
柳岸津(ユ・アンジン)「自画像」魂の発見
自画像 柳岸津 奇延修(キ・ジョンス)訳
生涯を生きてみると
私は私は雲の娘であり、風の恋人なので
雨と雲が、雪と霜が
川と海の水が他でもないまさに私だった事を悟る
ワシミミズクの鳴くこの冬も真夜中に
裏庭の凍った畑を駆る雪風に
心をゆすぐ風の恋人
胸の中に溶鉱炉に火をつける恍惚の嘘を
あぁ、夢中なだけでどうもできない憐れな希望を
私の分として今日の分として、愛して流れること
熟すほどエビの塩辛がおいしくなるように
垢が染みるほど人生がそれらしくなるように
生きるということも愛するということも
垢がついて汚くなり
真実より虚像に感動し
正直さより罪業に恋いこがれ
どこかへ休まず流れていくのだ
いっしょに横になっても互いに別の夢を見つつ
どこかへ休まず流れていくのだ
遠く遠く離れるほど胸はいっばいに満たされるのだ
果てまで行って帰ってくるのだ
空と地だけが住処ではないのだ
虚空がむしろ住む価値があり
漂い流れる事がむしろ愛することなのだ
振り返らないだろう
ふっと振り返れば
私は私は 流れる雲の娘であり
漂う風の恋人であった
※
とても勢いのある詩だと思います。ひとつひとつの言葉、比喩、イメージ、そして構造、すべてに於いて勢いが感じられます。
その勢いを支えているのは、ひとりの人間の生き方であり、更にもっと深く魂のようなものだと思います。
自然や歴史、そして多くの人々とつながっているものなのかも知れません。だから時には自分の力ではどうしようできない程荒々しくあり、人はそれで黙ってみているしかないのでしょう。
第一連に私はそんなひとりの人間と魂のドラマをみるような気がしました。つまり、これが自画像の
枠なのだと思います。
第二連以降は、その自画像のデティールが鮮やかに、しかも勢いよく突風のように描かれています。
私はこの詩を読んでいてゴッホの自画像やムンクの「叫び」などを思い出しました。
最終連を読むと、魂と向き合って生きていくこの詩人の覚悟が伝わってきます。
生涯を生きてみると
私は私は雲の娘であり、風の恋人なので
雨と雲が、雪と霜が
川と海の水が他でもないまさに私だった事を悟る
ワシミミズクの鳴くこの冬も真夜中に
裏庭の凍った畑を駆る雪風に
心をゆすぐ風の恋人
胸の中に溶鉱炉に火をつける恍惚の嘘を
あぁ、夢中なだけでどうもできない憐れな希望を
私の分として今日の分として、愛して流れること
熟すほどエビの塩辛がおいしくなるように
垢が染みるほど人生がそれらしくなるように
生きるということも愛するということも
垢がついて汚くなり
真実より虚像に感動し
正直さより罪業に恋いこがれ
どこかへ休まず流れていくのだ
いっしょに横になっても互いに別の夢を見つつ
どこかへ休まず流れていくのだ
遠く遠く離れるほど胸はいっばいに満たされるのだ
果てまで行って帰ってくるのだ
空と地だけが住処ではないのだ
虚空がむしろ住む価値があり
漂い流れる事がむしろ愛することなのだ
振り返らないだろう
ふっと振り返れば
私は私は 流れる雲の娘であり
漂う風の恋人であった
※
とても勢いのある詩だと思います。ひとつひとつの言葉、比喩、イメージ、そして構造、すべてに於いて勢いが感じられます。
その勢いを支えているのは、ひとりの人間の生き方であり、更にもっと深く魂のようなものだと思います。
自然や歴史、そして多くの人々とつながっているものなのかも知れません。だから時には自分の力ではどうしようできない程荒々しくあり、人はそれで黙ってみているしかないのでしょう。
第一連に私はそんなひとりの人間と魂のドラマをみるような気がしました。つまり、これが自画像の
枠なのだと思います。
第二連以降は、その自画像のデティールが鮮やかに、しかも勢いよく突風のように描かれています。
私はこの詩を読んでいてゴッホの自画像やムンクの「叫び」などを思い出しました。
最終連を読むと、魂と向き合って生きていくこの詩人の覚悟が伝わってきます。
長田典子「もしもできたら」言葉と一緒に [something blue]
もしもできたら 長田典子
できたら
犬のポチのときみたいに
湖の見える山の斜面に埋めてください
心臓の辺りに小さな梅の木を植えてください
二月のある日 白い花が
冬の花火のように満開になる頃
漣のように甘い匂いが広がるでしょう
鳥が乳のように蜜を吸い 囀るでしょう
誰かが ふいに振り向いて言うでしょう
もうすぐ暖かい季節が始まると
できたら もしできたら
※
私の場合、ひとつの詩を書くのに何日も何日もかかるときと、一時間もかからずにあっという間に
できる場合があります。そして、このことは誰もが同じではないかと思います。
しかし、よく考えてみると、これは不思議なことのような気がします。一時間足らずで、できるときは、まるで風が吹いてきたように、ふあっとできます。
あるいは小鳥の声がきこえてきたかのようでもあります。
ところでこの詩は、あるとき詩人の中にふあっと生まれたものではないかと感じます。ひとつの詩としては決して深遠な詩であるとか、鋭い詩とかいうものではありませんが、何とも今生まれたばかりのような初々しさがあります。(恐らく、この初々しさはいつになっても消えることはない)
こういう詩は書けそうで、しかし、決してそうではありません。いつもいつも、言葉と一緒に何かを
考えている、言葉と一緒に何か悩んでいる、
そうしたなかから初めて生まれるのだと思います。
そのひとつの証が最後の言葉にあります。「もしできたら」、この言葉が私のこころの奥に響いてきました。
できたら
犬のポチのときみたいに
湖の見える山の斜面に埋めてください
心臓の辺りに小さな梅の木を植えてください
二月のある日 白い花が
冬の花火のように満開になる頃
漣のように甘い匂いが広がるでしょう
鳥が乳のように蜜を吸い 囀るでしょう
誰かが ふいに振り向いて言うでしょう
もうすぐ暖かい季節が始まると
できたら もしできたら
※
私の場合、ひとつの詩を書くのに何日も何日もかかるときと、一時間もかからずにあっという間に
できる場合があります。そして、このことは誰もが同じではないかと思います。
しかし、よく考えてみると、これは不思議なことのような気がします。一時間足らずで、できるときは、まるで風が吹いてきたように、ふあっとできます。
あるいは小鳥の声がきこえてきたかのようでもあります。
ところでこの詩は、あるとき詩人の中にふあっと生まれたものではないかと感じます。ひとつの詩としては決して深遠な詩であるとか、鋭い詩とかいうものではありませんが、何とも今生まれたばかりのような初々しさがあります。(恐らく、この初々しさはいつになっても消えることはない)
こういう詩は書けそうで、しかし、決してそうではありません。いつもいつも、言葉と一緒に何かを
考えている、言葉と一緒に何か悩んでいる、
そうしたなかから初めて生まれるのだと思います。
そのひとつの証が最後の言葉にあります。「もしできたら」、この言葉が私のこころの奥に響いてきました。